
言葉に救われた。
言葉に背中を押された。
言葉に涙を流した。
言葉は人を動かす。
私たちは信じている。
言葉のチカラを。
 |
(下は左図に記載されている文字です)
言葉に救われた。 言葉に背中を押された。 言葉に涙を流した。 |

H23/06/28 の朝日朝刊「オピニオン」で「野中 広務」と「橋下 徹」の 「君が代起立条例」争論の一部分と その後に掲載された「投書」を記しました。 下記のリンクへクリックをどうぞ。
|
![]()
老人をナメるなよ!
トシをとると、とかく耳が遠くなる。だから老人と話すときは、
ちょっと声を大きめに話すのがマナーである。
トシをとると、とかく目がかすむ。だから老人も目を通すような印刷物は、
活字を大きめにして印刷するのがマナーである。
トシをとると、とかく体力が衰える。だから「働くことしか能のない高齢者は、
死ぬまで働いたほうがいい」なんて思ってはいけないし、
たとえ思っても言わないのがマナーというものだ。
が、いまの世の中、こうしたマナーを身につけている人が少なくなった。
とくに若い人がそうだ。相手の立場に立ってものを感じることのできないような人のことを
「想像力貧乏」という。
ところで、NTTドコモのCMに出てきた太田老人(爆笑問題)の場合はどうか。
電波状態を調べにきた田中調査員(爆笑問題)に、「散歩にきたのか」と太田老人は聞く。
「いえ、調査です」という田中調査員の声が聞こえなかったのか、
太田老人は家の中から犬を引っ張ってきて、「ついでに頼む」と言わんばかりに
リードを渡そうとするのだ。
ま、この場合は、太田老人の日ごろの言動から見て、
わざと聞こえぬフリをしていることは明らかだし、
そこでのマの抜けた(マを生かした)やりとりが、このCMの面白さでもある。
そう、トシをとると、耳や目が遠くなるぶん、とかく老獪さが身についてくるものなのだ。
が、太田老人のおふざけに便乗して言えば、
ときには、こういう場合でも、この老人は耳が遠いのだと思ってゲームにつきあってあげるのが、
若い人たちのマナーである。
で、そのお返しに老人も、おとぼけの芝居がばれないようにせいぜい芸をみがくのが、
若い人たちへのマナーである(かもしれない)。
(コラムニスト天野 祐吉)
H21.09.17 「朝日 ザ・コラム」より
![]()
|
震える手で電灯カバー外す 気がつくと、もう夕方だった。空は高く深く青かった。1945年8月15日。敗戦を告げた正午の放送から時は止まり、世の中の音は失せ、姑も私もただ座していた。 ふと立ち上がり、縁側に出た。周りの林や田畑の木が風に揺れていた。……負けたんだ。胸が騒いだ。周囲は無音。「負けたんだ」。今度は声にして呟いた。向こうの農家に小さな明かりがついていた。 さっき、部屋の黒い電灯カバーに触れたが外せず、手はまだ震えていた。戦争は負けて終わった、灯火管制も無いから電気をつけていいのよ、そう言い聞かせた。静かな空に戦いの音はないか 私はカバーを取り電気をつけた。膝にまとわりつく息子の目に光が震え私は思わず泣きながら抱きしめた。姑は、大丈夫かい、と小さく聞いた。久々の光の下、私たちは蒸したジャガイモを頬張った。出征した身内は玉砕し、艦と共に沈み帰ってこなかった。その後は蛆のついた魚の配給を受けに走り回る日々。 間もなく逝く私は「戦争をするな」と声を大にして言う。 主婦 古田 静 (仙台市青葉区 88才) H21.08.15 朝日新聞 「声」
古田さんのこの想い、私にも全く同じ状況の経験をした。そして、この直後「民主主義」とは、何であるかが理解でず苦悩した記憶がある。 yuuji |
  私達も60数年前このことがハッキリと記憶に残っている、 この時代、日本の置かれた経済的な状況、国際連盟の脱退から暗雲が広がった。 当時の言葉で「ABC包囲網」に囲まれた日本は、戦うのみと国民に宣伝して、戦争に突入したのです。これ全て外交の幼稚さにあったのでしょう。 その後間もなく、市街地が焼け野原になった光景は、未だに脳裏に残っている。 また、軍事教練と称して皇居前に膝間ついたことも・・・、 情けなく思うのみ。 何が、「天皇家」なのか、 何が、「神」なのか、 この歳になっても分からず仕舞い。 yuuji |
![]()

 |
各政党が投票日まで約1ヶ月、思い思いのマニフェストを発表した。 左記は、「自民党」「民主党」が公表したものだ。 しかし、小泉自民党が過去に発表したマニフェストの結果は、何であったかが私には、忘れてしまい分からない。 こんな事ではいけないので、一応記録することにした。 4年後にこのマニフェスト結果を忘れずに検証しよう。 |
 |
これまでの「自民・公明」の連立政府は、数に任せての暴力政府であったと思わざるを得なかった。 特に、公明党は庶民の味方であるべき党が軍事拡大方向に走った感があった。 宗教と政治は、どう進んでいくのか・・・。 シッカと見守っていこう。 さらに、自民党に代わろうとしている民主党の今後は、数の暴力をどのように処理していくのか興味深々である。 09/08/04 yuuji |
![]()
 音楽評論家 奥田 恵二 |
◆ 裁判員制度「良心的拒否」の導入を 裁判員制度がいよいよ今年5月から実施されるにあたり、賛否両面にわたりさまざまな意見が述べられてきた。しかし、反対論の多くが、この制度が実生活におよばす差し障りや、不慣れな環境に身を置くことへの不安を論点としていて、より基本的な問題に立ち入っていないように思える。 司法制度にはまったくの門外漢である私も、裁判員になる可能性がある国民の一人として自省するとき、反対論にくみする。だが、論拠は異なる。「人を裁かない権利と自由」が、すべての日本国民に認められてしかるべきだという観点に立つからである。 日本国憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定しているし、第18条は「何人も……その意に反する苦役に服させられない」と規定している。裁判への参加が「苦役」だと感じるか否かは、個人の主観の問題で、一概に言えるものではなかろうが、自分の良心に照らし合わせて、自分には「裁き人」である資質あるいは資格が無いと断ぜざるを得なくなったとしたらどうか。これは、国家ですら動かすことのできない最終的な個人の判断である。それにもかかわらず裁判への参加が求められるとしたら、その時点で、国家権力による個人への苦役の強要になり、信教の自由を侵すにも等しい行為になると思う。 もし、裁判員制度の導入が不可避ならば、「良心的兵役拒否」の制度を実施している国々にならい、「良心的裁判員拒否」制度を施行してしかるべきだと思う。時間的拘束を逃れるための単なる言い訳のために「良心」が悪用されるおそれがあるのだったら、諸外国で良心的兵役拒否者に課されるのと同じような代替奉仕活動を課すこともできるのではなかろうか。 自分が選ぶ時間に、事務作業や労務作業など「無色」の労働への従事を求めることにより、国家に対する国民の義務が果たせることになり、卑怯者の汚名を着せられるおそれもなくなる。 今回施行される裁判員制度は、殺人や強盗致傷などの重罪を扱う裁判に通用されることになるという。日常的に冤罪や、やり直し裁判の報道に触れている一般国民にとっては、専門の裁判官ですら判断に苦慮する事件にかかわれと言われても、そう簡単に引き受ける覚悟ができないのは当然であろう。 しかし、もっと恐ろしいのは、自らの良心に探りを入れることもなく、気軽に裁判員を引き受けた人物が、ゲーム感覚で裁判に参加し、軽々な判断を示すことにより、取り返しのつかない結果を招くことである。憲法第37条第1項は「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」と定めているが、はたして新制度のもと、「公平な裁判」が保証されるか、非常に危惧されるところである。 私はアメリカ音楽の研究者として1960年代から70年代にかけて、ベトナム戦争下でのアメリカで暮らした。自らの良心に照らし合わせ、理不尽と断ぜざるを得ない戦闘への参加を国家が求めたとき、それへの不服従を市民として表現するために、良心的兵役拒否を訴えた若者が少なくなかった。 裁判員制度について、どうしても同調できない者のために良心的拒否を制度化し、国民一人ひとりの「心の自由」を保証する道筋を開いておくのが、民主国の政府の責任だと思う。 |
![]()
  |
無職 下村 三郎(東京都昭島市 66) 「歳出削減の努力をした上で足りないものは国民にお願いする」。そんな閣僚らの聞こえの良い発言も、本音は消費税増税ということのようだ。政治家の言葉の裏の本音を見抜かないといけない。 自民党が無駄撲滅の削減案を作っているが、政府は来年度予算でも社会保障費の自然増を2200億円抑えようとする。国民の福祉は切り捨てても米軍への思いやり予算2千億円は減らさない。 「厚生年金赤字5・6兆円」という(9日朝刊)。国民年金も8千億円近い赤字だそうだ。積立金の運用損が原因と言えばもっともらしいが、要は国民の金を投資に失敗してスッたということ。 「国民の目線」というのが首相のうたい文句だが、お年寄りには姥捨て山の後期高齢者医療制度を押しっけ医師不足も深刻だ。生活保護認定の抑制で福祉が人を殺す。これで何が庶民の目線か。 政治家も身を切る、として議員定数を減らす動きもあるが、本音と建前を使い分け、財界の言いなりの人ばかりになってはたまらない。ますます国民の政治を見る目の確かさが求められている。 08.08.20 朝日「声」欄に |
 |
私たち後期高齢者といえども、政治を見る「確かな目」の昂揚が必要である、投稿者下村さんは、要点をよく捕らえていると思いますが、皆さん如何ですか、私は同感である。 yuuji |
 |
08.05.18 朝日の「耕論」に 雨宮 「それって蟹工じゃん」。こんな言葉を耳にしたのは、日雇い派遣などで働く若者が08.05.02日に岐阜県で開いたメーデーの場であった。・・・・省略・・・ 昨年の春には、自分たちを搾取する社会について学ぶため「資本論」の勉強を始めたという20代の派遣社員に話しを聞いた。 ◎ 細切れの低賃金労働、過労死寸前の長時間労働で働かされる現代の若者には、 経済のグローバル化と称し、そして、小淵政権後に生まれ始めた「自己責任論」機会の不平等を無視した収入の違いは、「能力・努力について」の結果だとする格差の正当化は、正しいのだろうか。考えるほどに難しい。 Yuuji
|
|
市井の片隅に生きる町人を描く、作家藤沢周平の筆はやさしい。同じ視線なのだろう。若いころ、(メーデーは過ぎて貧しきもの貧し)と詠んでいる。結核で長く療養中の自らを写した旬だったかも知れない ▼資本の論理が牛耳る世の中への、ささやかな異議申し立てのようでもある。同じころ(桐咲くや田を売る話多き村)とも詠んだ。郷里の山形のことか。どちらも、戦後復興の日陰に生きる人々を見つめて切ない ▼メーデーのきのう、各地で労働組合の集会があった。近年は地域や団体で開催日がば らつき、様変わりぎみだ。既成の労組だけでなく、低収入で厳しい生活を強いられている人たちの連携も、じわり広がっている ▼「プロレタリアート(労働者階級)」ならぬ「プレカリアート」と言うそうだ。イタリア語の「不安定」に由来し、非正規の労働者などを総称する。働けど食えない人もいる。「生存を貶めるな」と訴える集会がいま、全国で順次開かれている ▼はるか昔、聖徳太子は十七条憲法で「富者の訴えは石を水に投げるようだが、貧者の訴えは水を石に投げるようだ」と戒めた。富む者は聞き入れられ、貧者ははね返される。いまに通じるものもあろう ▼そうした、政治に届きにくかった労働現場の声が、様々な形でまとまり、噴き出し始めた。政財界は、はじき返すことなく、ていねいに聞く必要がある。メーデーは過ぎてー一あすは憲法記念日。格差は広がり、貧困ははびこる。「健康で文化的な」と生存権をうたった25条を立ち枯れさせてはなるまい。 08.05.02 朝日新聞 「天声人語」から 650年頃に上記のように「富者」と「貧者」を見分けていたことを知ったが、事実であったとすれば現代の政治は、何だろうかと胸が痛む。 yuuji |
 |
後期高齢者医療は 「自己責任」と「痛みを伴う改革」の狭間に入り、これがどういう方向に向かって進み、どんな内容に落ち着くものか想像もできない。 さて、「自民」対「民主」の戦いは、 どんな形に変化されるのか。 |
 どこの社会でも挨拶は絶対欠かせない、 |
挨拶の大切さ小4に教わる 高校教師 佐伯 雅弘(千葉県八千代市47、) 所用で行った四国からの帰路、新幹線の京都駅で男の子が1人乗り込み、私の隣に座った。小学4年という。富士山の絶景を眺めながら、プロ野球の話をし、男の子からチョコレートをいただくなど楽しく過ごすことができた。 その子は新横浜で降りるため、別れ際に丁寧に拶拶して外に出た。と、ここまではよくある話だ。驚いたのは、その直後だ。ふと、ホームを見ると、何と窓越しに男の子と、お母さんらしき女性ら家族の方々が全員で私に向かって手を振って挨拶したのだ。 私は言いようのない感謝の念で礼を点したが、もしホームを見なかったらと思うと申し訳ない気持ちにもなった。 最近「誰でもいいから人を殺したかっ」という若者の悲しい事件を耳にするが、その一瞬は、互いにどこの誰とも分からない関係にもかかわらず、うれしかった。男の敬意さえ感じるとともに、挨拶を大切にして生きねばと教えられたような気がした。 |
 今年もベランダに咲いた野草 |
若者に「信じられる未来」を 物欲が満たされると、次に人は知識欲を満たそうとする。 現在まで人間に生きがいをもたらしてきたのはこの二つの欲求だそうだ。しかし人は知識欲にも飽き始め、特に若い人は生きるエネルギーが喪失しかけている、と佐藤さんは看破する。だが、新しい夢の創出にコンピューターのシミュレーション技術が大きな力になりえると言う。 佐藤さんは約45年にわたり、電子工学、宇宙空間科学、核融合プラズマ科学などのさまざまな分野でシミュレーション研究を続けてきた方だ。その後、日本で開発され世界一の演算性能(2002~06年まで世界トップ)を誇るスーパーコンピューター「私が伝えたいのは、地球レベルから個人の将来まで、未来を覗くことが、人にとってどれだけ強い欲求かということなのです。コンピューターの進化によって、未来を覗く望遠鏡のように垣間見ることが可能になってきた。つまり、人間にとっての新しい生きがいが創出できる。やるべき未来の仕事が、若者の前にも見えてくるのです」 「地球シミュレータ」を駆使し、気象変動などに関する世界的な実績を残している。 たとえば商社に入って自分の力を生かしたいと考える。途上国の環境を守り、育てつつ、いい食材を日本に輸入するとしたら、どこから何を始め、何年後に実現できるのか。現存のデータをきちんと入力すればコンピューターはかなりの精度で予測ができるそうだ。その間に自分は何を学ぶ必要があるか、などプログラミングに組み入れていく。 あるいは閉塞感のある科学の世界も、未来に目を向けることで開かれる。 「自分がある仕事を目標にしようと考えたら、シミュレーションをする。人間が未来を歩いていこうとする意欲は歩く道筋が見えるから湧き上がるのです。直感や精神力だけではない。道路の明かりを目指して歩くようにね(笑い)」 コンピューターは、人間が岐路に立ったときの未来予測の道標になるのだ、と。その概念を世界規模から一人の若者にまで。佐藤さんに見えている未来は大きい。 |
![]()
 絵は:水沢貴子 |
ところが、悪いことに、漱石の要・鏡子は大の朝寝坊。漱石は日記にさんざん妻の悪口を書いている。「妻は朝寝坊である。小言をなお云ふと猶起きない、時とすると九時でも十時でも寝ている。洋行中に手紙で何時に起きるかと聞き合わせたら九時頃だといった」(1915年) 鏡子は明治の女にしては、なかなかの大物だ。 こんな鏡子を悪妻という人もいたが、これほどずぶとい女性でもなければ、神経過敏な漱石の要は続けられなかった。「あの母だからこそ、あの父と、どうやら、やっていけたのだと、むしろ褒めて上げたい」と、2人の長女・華子はのちに書いている。 (茨城大准教授・磯田道史) |
 |
さらば「再編」 07.10.23(火)の朝日朝刊に掲載された「政・態・拝・見」でのイラストです。二人の表情が余りにも似ていることから・・・・。 また、星 浩氏が書いていた 「俺はいま 何党だったけと 秘書に聞く」政界再編の様相が。 イラスト:郭 溢氏 |
 |
私の子供なら お尻をたたく 主婦 花畑 喜久子 (広島県福山市 62歳) 「ああ驚いた、驚いた」。 安倍首相辞任のニュース速報を見た私の感想である。 そのうち行き詰まって辞めるだろうとは思っていた。だが、参院選大敗の後、国民多数の意に反して辞任しなかった人が、国会で所信表明をした後、しかも代表質問の直前に辞意表明とは。 わがままな子どもの投げやりとしか、言いようがない。 辞任の理由はどうであれ、これから審議しようという法案が、成立しそうにないからといって、「辞める」というのは一国の長として、無責任のきわみだ。 首相はインド洋での海上自衛隊の給油活動は国際公約と言っていたが、すべての国民だけでなく、国際的にも恥ずかしい話だ。日本人のモラルがとやかく言われるが、まさにモラルのない首相としか言えない。 私の子どもだったら、「そんなことでは、これからだって生きていけないよ」と言って、お尻をひっぱたいてやるところだ。 当面の政治の混乱だけでなく、国民に植え付けた政治不信の深さが恐ろしい。 朝日 「声欄」に首相辞任の翌日掲載 投げやりな、責任を感じられない首相の行為に対して、子ども達には、どんな反応を与えることになるのでしょうか 辞任に対しての真実を知ることは出来ないが、どうも、しっくりしない事が多い。A級戦犯の孫とは「精神的に弱い育ち、環境」に原因しているのかも知れない。そして議員を辞めずに居座る行為には、アキレルばかりです。 |
 |
ご飯炊くのは、ぼくの仕事だ 
小学生 田中 望(兵庫県西宮市12歳) 学校から帰宅したあとのぼくの仕事は、ご飯を炊くことと、洗たく物をたたむことだ。両親が働いているから、この二つはぼくに任されている。 今日も、ご飯がおいしいと言ってくれるかなあ、と思いながら米をといだ。そして夕食の時間。炊飯器を開けた。いつもと様子が違う。炊きあがったご飯を少し食べてみた。ちょっと硬い。しまった。水の分量をまちがえたようだ。その日の夕食に、ご飯はなかった。 「ごめんなさい」という気持ちでいっぱいだ。家族に何度も謝った。「気にしなくてもいいよ。たまには失敗もあるよ」と父母。自分がご飯を炊かないと、夕食が成り立たない。ぼくの仕事の重みを感じた。これからも、一生懸命に家族のご飯を炊こうと思う。 07.08.19 朝日「声」欄に <この時代に、と思うほどの家庭の繋がりを感じました、私達の子どもの頃を思い出された> |
|
父親と子どもの会話 「自衛隊のこと キミどう思う」 通信教育指導員 川戸珠実 「自衛隊は必要だと思う。それとも必要じゃないと思う」。学校で聞きかじってきたのか、小学6年の息子が尋ねてきた。 「キミはどう思う」 「必要ないよ。憲法で禁止されてるし」 「でもよその国が攻めて来たらどうする」。うーんと口ごもる息子に、答えのつもりで日頃考えていることを語ってみる。 「よその国が攻めてきたらっていう、前提がおかしいんだよ。攻めてくるとしたら、何か原因があるからだよ。だとしたら、原因をつくらないことがまず大事じゃない。よその国と仲良く出来ることの方が、武器を持つよりも国を守ることになるという考えで、どうだろう」私たち自身は外交政策を決めたり、友好を進める法律を作ったりすることはできないけど、それをやってくれる代表を選ぶことはできる。そこまで話すと、「ああ、選挙だ」と息子。 今回の参院選は憲法改正の発議に関わる可能性のある議員を選ぶ初の選挙だ。息子と会話するうちに、年金問題や閣僚の不祥事などで、この争点がかすんでいるのが心配になった。 07.07.20(金) 朝日 「声」から 私にも、こんな子どもの関わり合いがあったことを懐かしく思い出されました。 軍備の増強に、虎視眈々と目論んでいる「A級戦犯者の3代目」とそのグループ達に 翻意させる手だては無いものでしょうか、私達にあるとすれば、「選挙」による意志 の表示をすること、そして、少しでもいい 踏み込んだ行動でしょうか。 |
![]()
|
監視社会はすぐそこまで近づいている、いやそこにいる。 あなたの顔から一瞬のうちに身元を割り出す。 近い将来には、空港で、会社の受付で、また銀行で、人々は身分証明書やパスポート代わりに、 自分の目を機械に見せるようになるかもしれない。 こうした新技術の登場は、私たちの社会に大きな変化をもたらす。 文=デイビッド・シエンク ジャーナリスト 写真=ジョージ・スタインメッツ 
世界一の監視国家 英国 2002年、ロンドン市内を走る2階建てバスの車体に「監視の目が市民を守る」という宣伝文句が登場した。 時は、ジョージ・オーウェルの小説『1984年』を連想させるそのトーンに、悪い冗談だろうと思った市民もいた。 だが、それは当局の真面目なメッセージだった。英国はひょっとすると世界一の監視国家かもしれない。全土に設置された400万台以上の防犯カメラのなかには、ワイパー付きの回転するカメラまである。 60年代から設置が進み、ゴミの不法投棄から強奪、脱税などの犯罪捜査に役立ってきた。今はテロ防止の手段にもなっている。 マンチェスターでは、治安当局者が通りや公共スベースの様子をモニターでチェックしている。 ・もう隠れられない、トラックの荷台の中が丸見え ・どんなに変装しても顔を見分ける(顔認証システム) ・服の下まで丸見え裸同然に(後方反乱X線で) ・監視ネットワークは、あなたを会社でも、通りでも見ているのです。 |
 |
<語りつぐ戦争> 村長を惨殺し持参の金強奪 無職 堀岡 新次郎 中国福建省福州の南西、沿海部の高台に駐屯地はあった。終戦間近の1945年の中ごろのことである。小隊編成の部隊は、出没する便衣隊(ゲリラ)を掃討するため、すげ笠にポロの野良着姿で出撃した。 小隊長の命を受けた下士官が村に潜入し、村民の安全を保証する代償として村長に金を強請した。数日後に部隊を訪れた村長はたちまち捕縛され、持参した金は巻き上げられた。 私の任務は、彼を営庭の木にくくりつけ、徹夜で彼のための穴を掘ることであった。 強奪された金が何に使われたか、村長がなぜ殺されたのか、すべては闇の中である。 首が切断された時の滝が落ちるような血の轟音は、今も生々しく耳に残っている。悪夢のような無残な事件であった。 07.06.15 朝日 「声」から |
 |
<あさひ ぴーぷる> 07.05.26(土) 「朝日夕刊」に [世界にはいろいろと平和に貢献している方が居るものです、「ピースボート」の名を耳にすると |
|
9条と現実の矛盾受け入れる憲法「選び直し」 文芸評論家・加藤典洋さんの『敗戦後論』が、戦争の死者の追悼のあり方をめぐって論争を引き起こしてから10年。 加藤さんは、かつては様々な間題を「戦争の死者の場所から」考えていたが、「ふつうの人の場所から」考えるようになった。その観点からすると、10年前の議論は安倍首相の主張のようにすっきりしすぎていた、と振り返る。憲法9条は理念としては素晴らしいが、自衛隊の存在という現実と乖離し「恥の多い」生涯を送ってきた事実から学ぶべきだった。では、その落差をどうするか。 ①理念に現実を従わせる ②現実に理念を従わせる ③現状維持、の三つの道がある。 加藤さんが選ぶ③は、矛盾を矛盾としてそのま受け取る。「他国が攻めてくると怖い、しかし、他国を攻めるようなことはもうしたくない」という人々の不安と願いに最もよく応える道だという。内田 樹・神戸女学院大教授の主張を踏襲する諭だが、そう考える背景を丁寧に述べている「敬愛する鶴見(俊輔〕さんには申し訳ないが」「畏怖する吉本〔隆明)さんには恐れ多いが」と思考を進める過稗はスリリングだ。 ( 07.05.01 朝日「文化」欄に ) <こういうことがベターであると考えていた、しかし、自民党・民主党に変えられてしまうのでしょう、 60年前のことを現実に知っている私のような高齢者にも、「国を守る」との4文字に惑わせられてい る方がいて、「胸元通れば暑さを忘れ」なのか。> <yuuji> |
| 「蟻 の 兵 隊」 奥村 和一 ・ 80歳、人生最後の闘いに挑む 監督 池谷 薫(いけや かおる)1958年 東京生まれ。 |
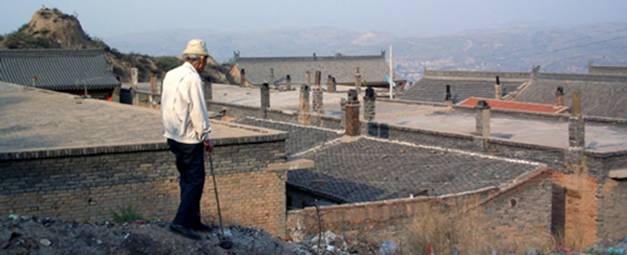 |
今も体内に残る無数の砲弾の破片。それは“戦後も戦った日本兵”という苦い記憶を 、奥村 和一 (80)に突き付ける。 かつて奥村が所属した部隊は、第2次世界大戦後も中国に残留し中国の内戦を戦った。しかし、長い抑留生活を経て帰国した彼らを待っていたのは、逃亡兵の扱いだった。 世界の戦争史上類を見ないこの“売軍行為”を、日本政府は兵士たちが志願して勝手に戦争をつづけたと見なし黙殺した「自分たちは、なぜ残留させられたか?」真実を明らかにするために中国に向かった奥村に、心の中に閉じ込められてきたもう一つの記憶がよみがえる。 終戦間近の昭和20年、奥村は「初年兵教育」の名の下に罪のない中国人を刺殺するよう命じられいてた。やがて奥村の執念が戦後60年を過ぎて、驚くべき残留の真相と戦争の実態を暴いていく。 これは、自身戦争の被害者でもあり、加害者でもある奥村が、「日本軍山西省残留問題」の真相を解明しようと孤軍奮闘する姿を追った世界初のドキュメンタリーである。 |
|
終戦当時、中国の山西省にいた北支派遣軍第1軍の将兵 59,000人のうち約2,600人が、ポツダム宣言に違反して武装解除を受けることなく中国国民党系の軍閥に合流。 「以下、投書です」 今の日本から戦争する気がなくても、9条が変わって集団的自衛権を行使できれば、アメリカが襲撃されれば同盟国である日本が報復しなければならなくなるのですよ。だから改憲を掲げた安倍首相を支持すれば、日本は戦争をするハメになるんです。間違いなく。これは誰が見ても間違いのない現実だと思うんですが。 蟻の兵隊見ました yuka 2007/01/30/01:06:59 No.276 平凡な一教師です。日本はもはや戦前であるという言葉を、子どもたちを再び戦場に送り出さなければいけない日が来るのではかと恐怖を感じています。「蟻の兵隊」の中には、現実の戦争を体験した奥村さんの人間としての部分、兵士としての部分が描き出されています。これをみて、教育の力の恐ろしさを実感せざるをえませんでした。戦争のできる国にしないために、子どもたちを戦場に送らないために、自分に何ができるか、自問自答する日々です。
|
|
私よりはるか年上の方が、権力に立ち向かっている、その行動力に、そして、三権分立と称している司法の方は、何を頭に描いて行動をしているのでしょうか。 この奥村さんは、自身が戦争の被害者でもあり、加害者でもあることの苦痛を抱えながら、山西省にわたって「罪の懺悔」をしながら、証拠調べを行っている姿(ドキュメント映画のよさ)をみて、つくづく感じうるところがありました。 この山西省事件については、過去に聞いたことはありますが、これまで深く知りえたことは無く、マスコミも言い伝えることが少なかったと思う。そして、奥村さんは旅団長か師団長でしょうか、最高責任者に対しての抗議の声が強く、このことが私の耳の奥に残った。 この映画は、都内そして全国で放映が続いています。インターネットでお調べください。 |
 「東中野ポレポレ」映画館では
「東中野ポレポレ」映画館では |
戦中、教育勅語を習いました。「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ‥…」。国家指導者に絶対的に従う精神を植え付けられ、私もその実行を願っていました。 日本の侵略や植民地支配に国民が向き合うべき姿勢を尋ねた質問に、大いに反省する必要がある」との答えが32%あったことは、世論の健全さを感じます。 外国から攻められない国をつくるには、国策に唯々諾々と従うのではなく、政府を監視し、必要な批判や抗議をしていくことこそ愛国です。それが、戦争をした世代の実感です。 |
 |
政治の不条理、私は忘れない
|
![]()

|
![]()
 |
「はい」は禁句、会話をつなぐには 俳優・演出家 わかぎ ゑふ さん 芝居を書き、演出をし、出演。テレビとラジオ、エッセーも・…‥。この夏は2本の芝居を抱えていたところに歌舞伎の演出が舞い込んだ。 「できるわけないやん」と一度は断った。でも歌舞伎は長年の夢。座頭の坂東三津五郎さんにも「大丈夫、できるよ」と背中を押され、腹をくくった。「こうなったらやり逃げや」。大盛況のうちに千秋楽を迎えた。 「物事の見方って簡単に反転できるんですよ」。多忙な日々を乗り切るコツ。「しか」より「も」で考える。 「2時間 しか ない、2時間 も ある、ぼら、変わるでしょ」 絵を措くのが好きで、役者になるつもりもなかった。少女マンガブームの高校時代、マンガをもとにした芝居の背景を頼まれた。ついでに、「役も足りないから出て」。これが原点だ。 ある時、大阪弁の芝居を書いていて気づいたことがある。 「会話の基礎編で話すのが東京。大阪は応用編なんや」。 「これ食べる?」って聞かれ「はい」と返事するのと、 「食べる食べる、それ好きやねん」と応じるのでは会話の展開が違ってくる。 「はい、はシャッターを閉める感じ。楽でしょうけど、本音でしゃべらないとわかり合えない」。だから、劇団で「はい」は禁句だ。 会話は人生最大の娯楽だと思う。「だから大阪人はおしゃべりと言われる」 |
 |
アジアでは人やモノ、情報の流れが加速し、国境の壁がどんどん低くなっている。一方で、ナショナリズムが高まる傾向があり、歴史問題を発端に中国や韓国で反日感情も強まった。ショナリズムの悪循環を絶ち「東アジア共同体」づくりへと駒を進めていくために、日本がなすべきことは多い。 ● 感情的な衝突が起きないよう、まず日本が歴史と向き合う。侵略の反省を行動で示す。 |
| 朝日「声」からさらに 核兵器には善意あるだろうか 隣国が核実験をした。 |
![]()
| 朝日「声」から 北朝鮮対応は、論議に節度を 大学非常勤講師 岩辺泰吏 (東京都足立区 63歳) 北朝鮮が核実験をしたと発表した。このような無謀は許されるものではない。しかし、こういう時にこそあえて、「論議に節度を」と言いたい。 米国の主導で、核廃絶会議を |
|
§ 北朝鮮制裁決議の骨子 ●国連憲章第7章の下に行動し、同章41条に基づく措置をとる |
§ 国連憲章第7章についてのキーワード 国連憲章第7章 安保理が平和への脅威や破壊、侵略行為を認めた場合、強制措置をとることができると定めている。第7章に基づく安保理議決によって、全加盟国に対して強制力を持つ制裁が可能になる。41条は経済制裁や外交断絶などの手段がとれるとし、42条は平和的な手段が尽くされたと判断された場合に武力行使を認めている。 (日本に住む私たちは、どうしても武力行使を拒絶しないと、どんなことになるかを、深く認識しなければならない。 yuuji) |
| 「天声人語」 平和に向かって そろって小さな手をあげて、園児が道を渡ってゆく。そばを犬を連れた人が通るじ色づいた木々の葉が散りかかる。こんな情景が身にしみるのは、深まる秋のせいだけではない。北朝鮮が核兵器を手にしたとすれば、今ここにある当たり前の平和が、いつか揺らぎかねないからだ ▼1914年に第一次世界大戦が始まった頃、ドイツの作家ヘルマン・ヘッセは「平和」という詩を書いた。 「みんなそれを持っていた。/だれもそれを大切にしなかった……おお、平和という名は今なんという響きを持つことか!(高橋健二訳) ▼開戦で、学者や作家は感激的な調子で愛国心をあおった。世界市民的な思いが強かったヘッセは、住んでいたスイスの新聞に書いた。 「愛は憎しみより美しく、理解は怒りより高く、平和は戦争より高貴だ」 ▼彼は裏切り者、売国奴とののしられ脅迫を受けたという。それでも二つの大戦に反対し続け、終結した45年に「平和に向って」を書く ▼「『平和!』だが 心は敢えて喜ばうとしない。/心には涙のほうがずっと近いのだ。/私たち哀れな人間は/善いことも悪いこともできる。/動物であると同時に神々なのだ!」。 度重なる戦禍の果てにようやくたどりついた平和の重みとかけがえのなさが感じられる ▼暴走する北朝鮮の「核」を、どうしたら不発のまま終わらせられるのか。この難問については、「国益」を超えた「人類益」の立場で、ことにあたってほしい。各国は今の世界にだけではなく、未来に対しても大きな責任を負っている。 06.10.12 朝日 「天声人語」 (分からなくなるのだ!, 誰か以下を教えて)、 どうして、核の保有国(米国等)が大きい顔をして、北朝鮮の核実験に対して反対するのかが分からない、核を持っていない日本が主張することは、正しいと思うのだが・・・?。 答えは簡単なはずだが、どのマスコミも言わない。 yuuji |
| 06.10.02(月) 横浜赤レンガ倉庫で「星野 富弘花の詩展」に友達と出かけた、その模様。 |
 |
 |
 |
| 過去に群馬県東村の「富弘美術館」に 行ったことは有るが、再確認のために でかけた。 |
この百合の花弁にタッチする繊細な筆 先にみとれてしまった。 自由のない手足にかかわらず、凄い |
桃の花との対話している様子が・・・。 |
 |
 |
 |
| 「美しい国」この方の発想が先です、 安倍総理 言葉を変えたら如何。 |
「ぐみ」との対話を良く表現している。 |
「そばの花」をみて、自分の指と比べている が、そのときの彼の心境は。 |
![]()
 日課とする朝の練習で滑らかな泳ぎを見せる 佐藤さん 佐藤さんとは、仙台の西公園のプール 開きに(古橋・橋爪・古川を招待するた めの困難な動きに)いろいろ関わったこ とを思いだされる。 なお、この西公園のプールは近々無くなってしまうことが決まったとのことで、何か 寂しい。 |
先輩OBの佐藤さんおめでとうございます 日本体協は12日の理事会で、長年スポーツを続け、世界記録などの実績を残した高齢者の功績をたたえる「第1回日本スポーツグランプリ」受賞者7名に、兵庫国体開幕の9月30日に神戸市内で表彰する。 ▽内田雪江(94)=熊本県、卓球 ▽佐藤利次(91)=宮城県、競泳 ▽天野耕兵衛(85)=石川県、剣道、ハンドボール、陸上 ▽宮本海(87)=静岡県、剣道 ▽守田貞義(90)=東京都、ラグビー ▽森田真積(92)=東京都、陸上 ▽原口幸三(96)=宮崎県、陸上 以下の主旨が、06.09.24(SUN)仙台「河北新報」に掲載された 「一番楽しい」と、泳ぐことは毎朝の日課。加えて飽くなき向上心が記録を伸ばしている。毎日泳ぐ距離こそ以前の半分程度の約600メートルに減ったが、推進力強化のために手や脚だけで泳ぐなど練習を工夫。 「漫然と泳いでも記録は出ない」と言い切る。ペースを上げるため自分より若い70代の選手と練習を重ねることも多いという。 現在、目と耳が少し悪い程度で、至って健康。「自分の記録を破ることが励みになっている。4年後に95―99歳の部で新記録を出したい」と意気軒高だ。 世界記録保持者原口幸三さん(96)=宮崎県=ら全国の80歳以上6人が選ばれた。 佐藤さんの競技履歴は75年、背泳ぎの選手として国体に出場するなど活躍。国内外の70歳以上の高齢者大会で世界記録を更新し続ける。以上「河北新報」 佐藤さんと私の出会いは、終戦の直後でした。 焼け爛れた電話局ビルの殺伐としてた職場でした、その頃ご一緒した方々とは、便りは途絶え、気がかりなときに兄よりの知らせによって、この快挙を知った。 佐藤さんは直腸に問題があって人口肛門での生活、さらに、糖尿病に犯されていることのことで、若い頃好物であった「酒」も断絶して精進の毎日であったことをお聞しました。 佐藤さん「本当におめでとうございました」。 若い頃お世話になったことが昨日のように思い浮かびます。 yuuji 1997.08 時点の記録 SPORTS 仙台から 1915年(大正4年)7月10日仙台市生れ。 仙台スイミングスクール所属。仙台水泳協会顧問。
|
![]()
|
「天声人語」 中世のドイツの町に不思議な男が現れる。男は、報酬をもらえるなら、人々を悩ませているネズミを全部退治してやると約東する。グリム兄弟の「ハーメルンの笛吹き男」の物語だ 06.09.16 朝日「天声人語」 |
「天声人語」 子供の視点から戦争を描き続けた、英国の児童文学者ロバート・ウ.ェストールに、「弟の戦争」(徳間書店)という作品がある。主人公は15歳の少年トム。両親と三つ年下の弟アンディと暮ら していた ▼1990年夏、そのアンディが突然、とりつかれたように意味不明の言語をしゃべり始めた。アラビア語だった。湾岸危機で従軍したイラクの少年兵の意織が、弟に乗り、弟は、ひとの苦しみに極めて敏感な性格だった。それまでも、写真で見た飢餓に苦しむエチオピアの子どもに、とりつかれるように感情を移入したことがあった。トムはアンディを助けようとするが、弟の意識はイラクの少年兵との間を行ったり来たりする ▼やがて米軍の猛攻が始まり、少年兵の目を通して戦場のむごさが伝えられる。それは、弟の体が目に見えない力ではねとばされるまで続いた。そのとき、少年兵は死に、弟は意識を取り戻した ▼戦争を見る目は、どうしても一方に偏りがちだ。地上の戦死者の姿が見えない映像では、本当の戦場は分からない。物語は、超人的な共感能力というフィクションを使って戦争を反対側からも描き、みごとである ▼ウェストールは、執筆後間もない93年に死去した。その後起こったイラク戦争では、子どもを含む民間人多数が巻き添えになった。イスラエルとレバノン過激派との紛争でも、同じ悲劇が繰り返されている。日本の私たちは、戦争の実相をどれだけ知っているだろうか。他者への共感能力の大切さを訴えた作品の重さを、改めて思った 06.08.23 朝日「天声人語」から |
![]()
 |
|
![]()
 湯川博士生誕100周年であると聞くが この写真を見る限り、当時のこのご夫 妻の様子が、仲睦かしく、そして、 微笑ましく感ずる  若い頃の吉田香代子さん  |
「核で殺した」ぼろぼろ涙 「アインシュタインは『罪のない日本人を殺して申しわけない』といって泣きはった。私たちの手を握り締め涙をぼろぼろ流して」 湯川スミはまるで昨日のことのように、小林康子(29)に話しはじめた。小林は東京の美術出版会社・世界文芸社に勤めている。04年9月、「8・15国際平和美術展」の打ち合わせで京都の湯川邸を訪ねたときのことだ。 1948年、湯川秀樹は、米プリンストン高等研究所に招かれ、妻スミと渡米した。アインシュタインが「会いたい」といってきた。ユダヤ人の天才科学者は、ヒトラーが原爆を先に手に入れるのを恐れ、米大統領ルーズベルトに手術を書いて核兵器開発を勧めた。しかし広島、長崎の惨禍を知り、深く悔いていた。スミの記憶「このままでは人類が滅びてしまうかもしれん。そうならんようにどうすればよかろうか。秀樹さんとアインシュタインが相談して世界連邦が一番いいとなった」 戦争をなくすために世界中の国々でひとつの連邦政府をつくろう。そんなユートピア思想は大戦前から欧米にあった。「夢物語にすぎない」とみられていたが、大戦のすさまじい破壊や原爆の恐怖が人々を振り向かせる。 46年、ルクセンブルクで世界連邦をめざす国際組織が生まれた。日本では敗戦の年の12月、尾崎行雄が国会に「世界連邦建設に関する決議案」を出した。日本人初のノーベル賞を受けて苦しい時代に人々を元気づけた秀樹は国際組織の会長を務め、81年に死去。スミは遺志を継ぎ、87年、名誉会長になった。 南画を描くスミは毎年、「8・15」美術展に出品した。ことしは3月に色紙を小林に渡した。原爆ドームの絵に、秀樹の詠んだ歌。 まがつびよ ふたゝび こゝに くるなかれ 平和をいのる 人のみぞここは 来年は秀樹生誕100周年。「忙しくなりそうやね」。小林が聞いたスミの最後の言葉になった。それから2カ月後の5月14日、スミは96歳で逝く。 秀樹は「世界連邦は昨日の夢であり、明日の現実である。今日は昨日から明日への一歩である」と呼びかけた。その夢にひきつけられた人々のなかに平凡社の創業者下中弥三郎もいた。 下中は大アジア主義者で大政翼賛会に協力し、戦後、公職追放になった。世界連邦運動に力を入れるようになり、52年のアジア会議に、東京裁判で「A級戦犯は全員無罪」と主張したインド人判事パルを招く。「日本無罪論」を唱えた評論家田中正明も下中と近く、この運動に加わった。 55年下中は核廃絶と憲法の平和主義をかかげて、秀樹たちと「世界平和アピール7人委員会」をつくる。 科学者朝永振一郎、作家川端康成らも入れ替わり名を連ねた。04年、翻訳家池田香代子(57)がメンバーに入った。 池田は学生時代からノンポリだった。01年、9・11同時テロとアフガニスタン攻撃に「ショックを受け、いても立ってもいられなくなって」、アフガン・パキスタン国境地域で診療する医師中村哲(59)の講演会を聞きに行った。 私にも何かできないか。池田は「世界がもし100人の村だったら」を出版し、ベストセラーに。印税をアフガン難民救援などにあてた。ことし6月、池田たちは米国とインドの 原子力協力に警鐘を鳴らすアピールを出した。委員会発足から数えて88回目だった。 宇都宮憲爾(80)は広島で育ち、弟や親類が被爆している。核廃絶運動に飛び込み、湯川夫妻と親しくなった。いま世界連邦運動協会の理事長。「昭和40年代までは運動に熱気があったが、その後は低調に。いくらやってもこれだという結果がみられず、失望感があったからでしょうか」 核を持つ国が増え、民族や宗教もからんで、火種は尽きない。それでも宇都宮は言う。「いくら夢物語だといわれようと、世界連邦しかない」。昨年8月、国会の戦後60年決議に「世界連邦実現への道の探求」という言葉が、盛り込まれた。未来への足がかりになると宇都宮は信じている。 (大室一也) 0608.23 朝日 「世界連邦夢で終わらぬ」から |
![]()
  |
「天声人語」 06.08.10 |
![]()
 |
嘆かわしい首相の論法 靖国神社参拝にこだわり続けた5年間の、小泉首相なりの最終答案ということなのか。それにしては、なんともお粗末と言うほかない。 3日付で配信された小泉内閣メールマガジンで、首相は年にl度の参拝に改めて意欲を示した。 そのなかで「私の靖国参拝を批判しているマスコミや有識者、一部の国」に、こう反論している。「戦没者に対して、敬意と感謝の気持ちを表すことはよいことなのか、悪いことなのか」悪いなどとは言っていない。私たちを含め、首相の靖国参拝に反対、あるいは慎重な考えを持つ人々を、あたかも戦没者の追悼そのものに反対するかのようにすり替えるのはやめてもらいたい。首相はこうも述べている。「私を批判するマスコミや識者の意見を突き詰めていくと、中国が反対しているから靖国参拝はやめた方がいい、中国の嫌がることはしない方がいいということになる」これもはなはだしい曲解である。 日本がかつて侵略し、植民地支配した国や韓国がA級戦犯を合杷した靖国神社への首相の参拝に反発している。その思いにどう応えるかば、靖国問題を考えるうえで欠かすことのできない視点だ。 ただ、それは私たちが参拝に反対する理由のひとつに過ぎない。首相の論法はそれを無理やり中国に限定し、「中国なにするものぞ」という人々の気分と結びつけようとする。偏狭なナショナリズムをあおるかのような言動は、一国の首相として何よりも避けるべきことだ。 その半面、首相が語ろうとしないことがある。あの戦争を計画・実行し、多くの日本国民を死なせ、アジアの人々に多大な犠牲を強いた指導者を杷る神社に、首相が参拝することの意味である。 戦争の過ちと責任を認め、その過去と決別することが、戦後日本の再出発の原点だ。国を代表する首相の靖国参拝は、その原点を揺るがせてしまう。だから、私たちは反対しているのである。昭和天皇がA級戦犯の合杷に不快感を抱き、それが原因で参拝をやめたという、側近の記録が明らかになった。国民統合の象徴として、自らの行動の重みを考えてのことだったのだろう。もとより中国などが反発する前の決断だった。 国政の最高責任者である首相には、さらに慎重な判断が求められる。 憲法に関する首相の強引な解釈もいただけない。憲法20条の政教分離原則は素通りして、19条の思想・良心の自由を引き合いに、こう主張した。「どのようなかたちで哀悼の誠を捧げるのか、これは個人の自由だと思う」 19条の規定噂国家権力からの個人の自由を保障するためのものだ。国家権力をもっ首相が何をやろうと自由、ということを定めた規定ではない。 こんなずさんな論法で、6度目の参拝に踏み切ろうというのだろうか。15日の終戦記念日に行くとも取りざたされるが、私たちはもちろん反対である。 06.08.04 朝日社説に |
![]()
 |
戦争起きても「戦わない」 日本が戦争に巻き込まれる危険性があると感じている方が急増している。内閣府の調査によると、94年は19.2%だったのに、今年2月は45.0%だった。朝鮮半島情勢関心があると答えた人が多かった。 一方、自衛隊や防衛問題に関心がない人が3割いる。理由は「よくわからない」が4割、「自分の生活に関係ない」が3割であった。60カ国で国民の価値観をきいた、世界価値観調査2000では、自国の軍隊(日本は自衛隊)を「非常に信頼する」と答えた日本人はわずか8.5%。上から43番目だった。「もし戦争が起きたら国のために戦うか」の設問に、「はい」と答えた率は最低。下から2番目のドイツの半 分以下だった。一方、「戦う」率が高かったのは、ベトナム、中国で9割。米、ロ両大国は6割台だった。第2次世界大戦で負けた日独が際だって低く、概して侵略を退けた国や戦争をし続けている国が高いことが目立つ。 日本は敗戦で不戦を誓った。この結果を「情けない」という必要はないと思う。 (坪谷英紀) 06.08.06 朝日 「be on Sunday」から |
![]()
 |
介護は一人で抱え込むと、苦しくなるけけど 芸能界で華々しく活躍していたアイドル・荒木由美子さんが突如、結婚・引退したところまでは知っていても、その結婚生活が新婚2週間目から介護一色に彩られていようとは。そして、21年ものブランクを経てテレビに再登場したとき、以前よりもさらに美しく年を重ねている姿に2度びっくりされた方が少なくないのでは。 |
 荒木 由美子さん  |
福祉番組のサブ司会が好評でした。障害や病気に前向きに取り組む方たち、各地で介護される方々と触れ合って感じたことは? |
![]()
|
「声」 朝日 朝刊 06.07.19 牧師 込堂 一博 (北海道旭川市 58歳) 3・1運動の史実直視して イスラエルを訪れた小泉首相は12日、ナチス・ドイツによるユダヤ人大量虐殺の遺品を展示する記念館で、「二度とこういうことをしては いけないと痛感した」と述べたという。 私は6月下旬、韓国を訪れ、ソウルの南50㎞に位置する「堤岩里」にある「3・1運動殉国記念館」を見学した。独立運動が拡大していた1919年4月、旧日本軍が20人以上の村民を教会に閉じこめ虐殺し、村の家屋にも放火したものだ。 国によって記念館が建てられ、多くの韓国人が見学におとずれている。加害者側の国民として何とも遣り切れない思いがした。ただ、救いだったのは、日本語パンフレットに「赦しこそすれ、忘れる勿かれ」という言葉と「日本人たちの募金により現場に教会が建てられた」と明記されていた。 教会の韓国人牧師が「日本各地で事件の講演をして歩いたが、日本人の多くは事件を知らなかった」と嘆いていた。殆どの韓国人の人々は知 っている。史実を直視する勇気を持たなければ、将来再び悲惨な事態を起こし兼ねない。 戦争の悲惨さを心に刻みたい。 ◎ 「満州国」の概要などについて |
![]()
「窓」 論説委員室から 06.07.18(水) 朝日 夕刊に 戦争体験は退屈か 「言葉が心に届かない」 |
|
06.07.02(日)朝日 Life & science に掲載 低きに流れない水 |
何故か、我が国小泉政治(経済)の仕組みも
低きに流れない金
に思われてならないが如何ですか。 yuuji
|
「天声人語」06.06.29 朝日朝刊
|
![]()
|
株で儲けたらなぜいけない 「頑張る人たち 報われる世に」(25日)を読んでいろいろ考えました。 頑張って学んだ結果、株で利益を得て生活するのがそんなに悪いことなのでしょうか。株で儲けるのも、なかなかできない立派なことです。 |
![]()
| 06.06.29(木)の投書 沖縄戦の事実を風化させるな 無職 宮島 幸宏 社説「沖縄慰霊の日」(23日)に、沖縄戦の悲劇を絶えず思い起こすことが「日本の進む道を考えるうえで、苦い教訓となるに違いない」と結ばれていた。 |
![]()
| 06.06.13(火)の投書 琉球の方々にお詫びしたい 23日は、61年前に沖縄戦の組織的抵抗が終わったとされる「慰霊の日」です。私はいつも、大和人として琉球のすべての方々に謝罪したいと思っています。 61年前の今ごろ、沖縄では15~17歳の少女までが死体だらけの洞窟の中で、日本兵の治療に尽くしていました。最後は日本兵からもらった手投げ弾で米軍に向かい、雨のような銃弾を浴びたのです。ひめゆり部隊の方々の死は、神風特攻隊員以上の悲しい死でした。 戦争は人間の心を変えてしまいます。当時は「鬼畜米英」と言っていました。でも、日本兵も多くの琉球の方々に、ここでは書けないような仕打ちをしました。日本国内で唯一の地上戦が行われ、父母やきょうだい、また大切な人を亡くされた方々に深くお詫びいたします。 大田昌秀前知事は「本土の人は沖縄のことをどう思っているのか」と涙ながらに語りました。約400年前の薩摩藩支配や明治政府の琉球処分など、大和人が琉球の人々に与えた苦しみはあまり報道されません。 日本に米軍基地は不要です。基地がなくなれば美しい沖縄で観光立県が実現し、より活性化するに違いありません。 ライター 川嶋 修司 (岐阜市 63歳) 06.06.13 朝日 「声」欄に 私達の意見・発言 狂気と悲劇を引き起こした責任のあった人々は、今何処に祀られて?、このことを思い起こすとき、沖縄の方々に対しては、投稿者が述べていることは当然です、しかし、狂気と悲劇をまき散らした人々をどの様に評価すべきでしょうか。 私たちは、私も、戦時中の「皇民化教育」によって「国の為に死を惜しまない」ことを教え込まれ、ただひたすらに走った、これは真実のことです。 yuuji 朝日の社説では「沖縄戦の悲劇と狂気を絶えず思い起こす。それは、日本の進む道を考えるうえで、苦い教訓となるに違いない」と・・・・。(06.06.23 の朝刊に) |
|
![]()
.
| 06.06.30 朝日 朝食抜き傾向1~3歳は1割も 1~3歳の乳幼児の約1割が朝食を食べないことがあり、寝る時間が遅かったり母親が欠食ぎみだったりするほどその傾向が強いことが29日、厚生労働省の05年度乳幼児栄養調査で分かった。 「ほとんど食べない」も2%おり、同省は「生活リズムが定着する時期で非常に問題。親の生活習慣見直しを呼びかけたい」としている。 母も欠食がちだと「食べる」の5倍に 政府は今年3月に決めた食育推進基本計画で、朝食をとらない子どもは、「小学5年生で4%」(00年度)としているが、乳幼児の実態が分かったのは初めてだ。 調査は85年から10年ごとに実施し、05年度が3回目。全国2305世帯の母親を通じ、2722人の乳幼児を分析した。朝食を「ほぼ毎日食べる」と答えたのは90・6%で、「週に4~5日」が5・4%、「2~3日」と「ほとんど食べない」がそれぞれ2・0%と、欠食がある乳幼児が1割近かった。 母親の朝食習慣との関係も調べた。母親が「毎日食べる」場合は欠食のある乳幼児は6%だが、「ほとんど食べない」では29・8%にのぼった。 就寝時刻との関連では、午後8持前に寝る乳幼児で欠食があるのは、2・9%だが、10時台は13・8%、12時以降は50・0%だった。朝起きられないことが、食欲不振や朝食の時間のなさにつながっているとみられる。 |
![]()
 |
朝食と学力の深い関係 |
こんなことを見ていたところ、翌日06.06.19 の朝日で
「どうする子供の朝ご飯」と題して
女子栄養大副学長 香川 靖雄さん、
福山平成大客員教授 鈴木 雅子さん
香川 靖雄さんは、「学校給食こそ最後の砦」と
鈴木 雅子さんは、「家庭での食生活が大切」だと話している。
これは、「食育推進基本計画」なるものの中で、朝食を採らない子供を4%から0%にするとの目標をかかげる中、朝ご飯を提供する学校が
出始めている。とのことであります。
「家庭や親が本来の役割を果たせないでいる」。
どうして、日本が米国追従になってしまったのか、米国は1975年から実施している、とのことです。
「忙しくて準備出来ない」「作っても食べない」ことを理屈に、手抜きをする、これが本音ではないでしょうか、
また、こんな質問があったとのこと
「私と夫は、結婚前も結婚してからも、一度も朝食をとったことがない、体調には何の問題もないなぜ子供に朝食を食べさせなければならな
いのか」?と
私達の意見・発言
さあ、皆さんそれぞれの答えは、いろいろなことになるでしょう。
私(yuuji)には「想定外のこと」でした!)
06.06.20 私は詳しく朝日の内容を読んで考えてみました。 yuuji
![]()
「武士道」で経済を救う
06.06.17 朝日「News Inside」から
 |
拝金主義の世相を憂える人々がすがる |
金儲けだけがすべて。違法、脱法もいとわない拝金主義がまかり通る世相を憂える人々が、武
士道にすがろうとしている。藤原正彦さんのミリオンセラー「国家の品格」でも復活を提唱され
た武士道精神に、大義や人間性を惜しげもなく手放してしまったために、いまになって血の気を
失っている日本経済の再生まで託せるのだろうか。
(保科龍朗)
墓石と墓所を販売して70年余。盆と彼岸は1日数万人が墓参する垂只都立八柱霊園の近くにある
石材会社(千葉県松戸市)は、電話帳を頼りにひたすら電話をかける数十人のパート主婦が営業の
前衛だ。無作為に電話して感触を探り、手応えをつかんだら営業マンを訪問させる。この石材会社
である日、会議室にパートの主婦たちが召集された研修に同席してみた。40代から50代の主婦た
ちは午前中の3時間、夢うつつにもならずに講師のこんな言葉に耳を傾けている。
「武士道にならった愛社精神とは自己犠牲を強いるものではありません。すべてが自発的なのです
。いま自分には何ができるのか、何がしたいのかを常に考えましょう」 営業にたずさわる従業員
のマインドに武士道精神を注入する社員研修を始めたのは、今年1月からだという。
月に1度、年12回にわたるプログラムには、新渡戸稲造の名著「武士道」や佐賀藩士、山本常朝
の口伝「葉隠れにあるような武士道の神髄を平易にかみくだいたフレーズがちりばめられている。
(中間の文省略)
良心に動かされ
約200年も戦火が途絶える江戸時代の天下泰平の世に、武士は軍役を担う戦士としての存在意義
を失った。領地からの年貢収入は保証されているから、酒びたりになって遊んで暮らす「遊民」へ
堕落してもよさそうなものだったが、日本の武士たちは、なぜかその特権を潔しとせず、有能な行
政官僚へ転化していった、と笠谷教授はいう。
「忠義」の観念も、軍事組織から行政組織に変貌し、終身雇用・年功序列制という日本型組織の
原型ともなった「御家」大事の忠誠心へと変質する。諌言、押込などという、良心に動かされて主
君に執拗に異議申し立てする制度が慣行となったのも、組織の手厚い身分保障があったればこそだ
った。
「バブル期に勤勉の価値を見失い、非情なリストラがまかり通って雇用が不安定になった『失わ
れた10年』に企業への忠誠心を喪失したいまこそ、恩義と剛直な自立心を併せ持った武士道モデル
の組織論が日本経済を雄々しく再生復活させる手がかりになる」と笠谷教授は力説している。
私達の意見・発言
![]()
(新聞などから END)